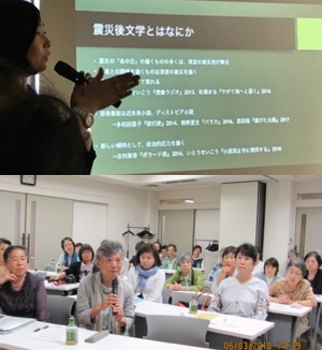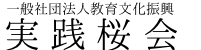2018年6月3日(水)11時〜12時
第42回、実践英文科会総会・講演会が開催されました。
総会:参加者40名 講演会参加者49名
総会 11時から12時
司会・進行:木村和子
議長:建部静代
以下の議題が審議され、承認されました。
議題
- 平成29年度活動報告(植松ちどり)
- 平成29年度収支決算報告(田光雪枝)
- 監査報告(横橋貴子)
- 平成30年度活動計画案 (植松ちどり)
- 平成30年度予算案(田光雪枝)
- 報告事項特命委員について(山内典子)
国際交流基金選考委員 成田貴三子)
以上
 講演会(13時〜15時)
講演会(13時〜15時)
“東日本大震災について文学が考えたこと”
講師 木村朗子氏KIMURASaeko
(日本文学研究者、津田塾大学国際関係学科教授)
(プロフィール)
木村朗子氏 KIMURASaeko
東京大学大学院総合文化研究科言語情報科学専攻博士課程修了。2004年「母、女、稚児の物語史:古代・中世の性の配置」で学術博士。専門は言語態分析、日本古典文学、日本文化研究、女性学。2010年女性史学賞受賞
*著書:「女子大で源氏物語を読むー古典を自由に読む方法」「女たちの平安宮廷ー栄花物語に読む権力と性」「震災後文学論ーあたらしい日本文学のために」他
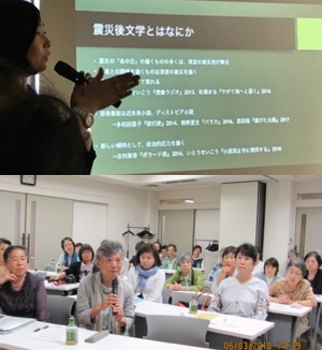
2011年の東日本大震災から7年が経った。この震災は日本だけでなく世界にインパクトを与え、文学、映画、美術など多様な分野で作品を生み出している。そうした作品は東日本大震災をどのように捉え、表現してきたのか。
言論統制の空気の中でタブーに挑戦する文学が興っている、それが震災後文学であると定義をし、いろいろな作品を紹介しながら、震災後文学論の現状が展開された。読み手の存在の有無にも言及し、被災地から遠く離れた地域や海外からの注目度が高く、読者からの作品への期待感にも触れた。

 講演会(13時〜15時)
講演会(13時〜15時)